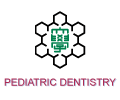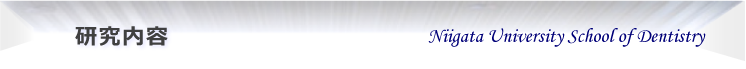1.臨床的な研究
近年、高齢者のフレイルに注目が集まり、口腔機能の維持向上を目指す様々な取り組みが社会に浸透してきています。小児期においても、一定の口腔機能が獲得できないことで、成人期に十分な機能が発揮できず、高齢期のオーラルフレイルに拍車がかかることが危惧されています。私達は口腔機能の育成における成長発達の指標を確立し、近年増加している口腔機能の発達が不十分な子ども達の『口腔機能発達不全症』への診断や治療に応用することを目指した様々な研究を行っています。
A.小児の口腔機能
三次元動作解析装置(VICON ®)や超高速三次元表面形態撮影装置(3dMD ®)、ステレオビジョンカメラおよび各種生体計測システムを用いて、小児口腔機能について包括的に研究しています。
- 乳幼児期からの摂食における食具動作の定量的分析
- 摂食動作における口腔と上肢、体幹との協調運動の発達変化の解析
- 捕食時口唇閉鎖に伴う口腔の圧形成パターンの解析
- 摂食と呼吸の関連性
- 顔面および口腔運動機能と軟組織形態との関連性
B.歯磨き
小児および障がい児・者の口腔保健には特段の配慮が必要です。歯磨きは国民の多くが毎日行う最も普及している健康維持に関わる行為です。しかしその一方で、その質についてはまだ曖昧な点が多いのが現状です。動作解析と歯磨きの歯垢除去効果について特許を取得するなどして、より質の高い歯磨き方法や歯ブラシの開発を目指した研究を行っています。
C.虐待児の口腔保健と生活習慣
近年、社会の口腔衛生に関する知識・関心が向上したことから、う蝕は顕著な減少傾向を示しています。その一方で、様々な理由から口腔の衛生管理が困難な人々への口腔保健支援についての必要性・重要性は高まっています。私達は、特別な配慮を必要とする子ども達への口腔保健支援プログラム構築を目的として、新潟県内の児童相談所や知的障害者施設と連携しながら、養育環境や生活支援の状況といった生活背景と口腔環境との関連性についての研究を行っています。
D. 歯の形成障害
歯の数や形・質には多くの因子が関与しますが、生まれつき歯の数が少ない『先天性欠如歯』は口腔の成長発育に影響を及ぼすことから、小児期からの継続的な口腔管理を行う上で慎重な対応が必要とされます。私達は、先天性欠如歯の疫学調査研究や治療薬開発を目指す研究の分担・協力研究機関となり、研究に協力をしています。